 キーワードその3「エネルギー関連触媒」
キーワードその3「エネルギー関連触媒」
![]() Q エネルギー問題?
Q エネルギー問題?
エネルギーと環境問題は切っても切れないフカ〜イ関係。いま人間サマが最も頼りにしているのが化石燃料と原子力。化石燃料は燃せば燃すほどCO2を発生し、地球温暖化問題を引き起こしています。エネルギーは経済ともフカ〜イ関係なので温暖化問題は国家間の政治レベルでも大問題です。CO2削減に向けた国際的な合意「京都議定書」の具体化案つくりであんなにもめているはそのせいですね。原子力はCO2をほとんど発生しません。かといって数々の事故に懲りて脱原子力を目指す先進国も出てきている状況です。世の中で最もクリーンなエネルギーって何でしょ?太陽光や風力はそりゃ確かにクリーンだけれど密度が低かったり、利用場所が限定されたりで、とても全地球的にメジャーにはなりそうにない。人間サマは有史以来もの燃やして生活してきたわけだから、何かしら燃料と言えるものが必要になります。燃料というエネルギーで最もクリーンなもの、それが水素(H2)です。
水素は燃しても水が発生するだけ。たしかにクリーン。燃料電池の燃料として脚光を浴びてます。だけど地球上のどこをどんなに掘っても出てきません。水素はつくらないとないんです。どうやってつくるか?水の電気分解って?冗談でしょ。エネルギーつくるのにそれ以上の電気エネルギー使ってどうすんの。工業的な水素製造法は炭化水素の水蒸気改質です。例えば、CH4+2H2O→CO2+4H2。この反応にも触媒が必要です。でもちょっと待って。これってCO2もドカドカできるんです。H2自体はクリーンでも、そのH2を製造するのにCO2が発生しては元も子もありませんなあ。
![]() Q CO2つくらずにH2つくる光触媒
Q CO2つくらずにH2つくる光触媒
CO2をつくらずH2をつくる画期的な方法は光触媒です。この触媒を水に入れて太陽光をあてると水素と酸素がブクブク。なんて触媒ができればノーベル化学賞間違いないほど、難しいというか、夢に近い触媒です。光触媒のアバウトな作動原理は次の図の通り。
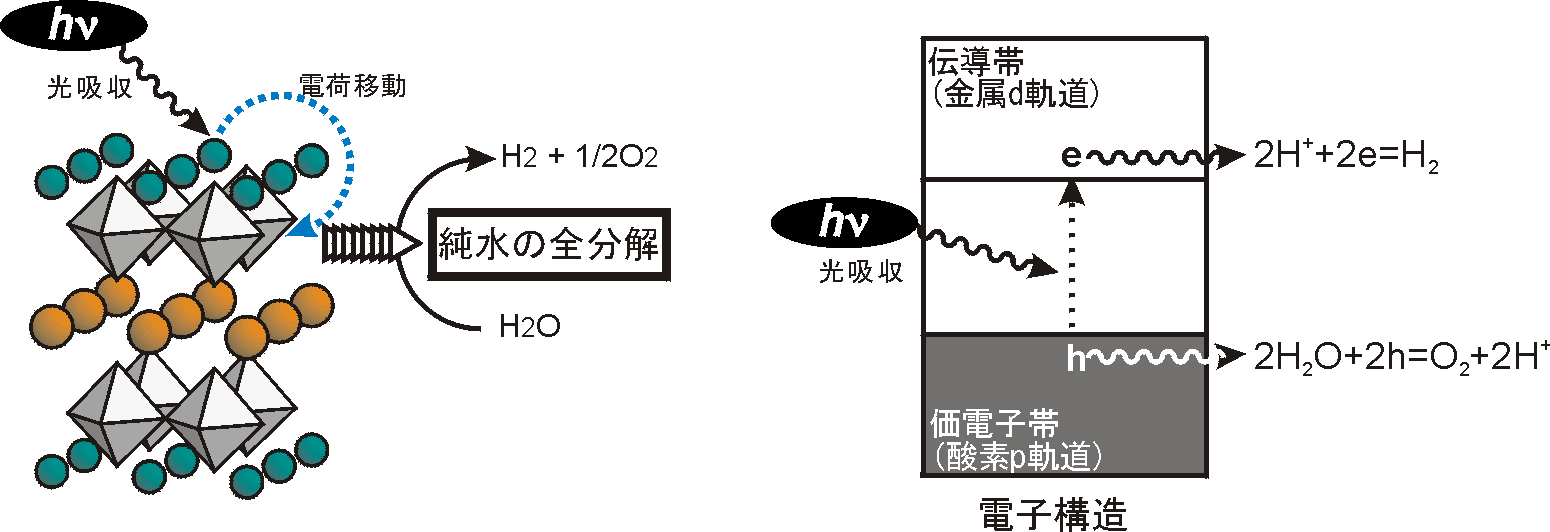 半導体光触媒の作動原理図。①価電子帯と伝導帯とのギャップに相当するエネルギーの光を照射、②電子励起によって伝導帯に電子(e)、価電子帯にホール(h)が生成、③電子とホールは半導体表面に移動して、水と反応し、それぞれ水素と酸素を発生する、つまり水の全分解が達成される。だから、光触媒の設計には電子構造が重要なファクタになるわけね。
半導体光触媒の作動原理図。①価電子帯と伝導帯とのギャップに相当するエネルギーの光を照射、②電子励起によって伝導帯に電子(e)、価電子帯にホール(h)が生成、③電子とホールは半導体表面に移動して、水と反応し、それぞれ水素と酸素を発生する、つまり水の全分解が達成される。だから、光触媒の設計には電子構造が重要なファクタになるわけね。
そもそも半導体光触媒はHonda-Fujishima効果として世界的に知られた大発見。また、水の全分解に活性な光触媒は最近、東工大の堂免先生を中心とする研究グループが画期的な材料を開発しており、日本が世界をリードしている。うちでは、もともと持っている無機材料合成および構造変換の技術を使って多様な新しい半導体光触媒を開発することを目的として6年くらい前に研究を開始しました。うちの学科で光触媒とか光有機化学とかは、保田・白上研究室が長く活発に研究されています。うちの特徴は、無機材料をベースとする半導体光触媒であること、そして化学反応そのものよりも光触媒材料の開発と作動原理の解明に力を注いでいることでしょうか。
![]() Q どんな実験やってんの?
Q どんな実験やってんの?
光触媒反応は、半導体光触媒(通常、粉末)を水に懸濁した状態でセルに入れ、下の写真にあるような閉鎖循環系装置に接続します。セルを真空排気してアルゴンガスを150torr入れ、非常に強い光源、例えば高圧水銀ランプやキセノンランプから発せられる紫外可視光を懸濁液に照射します。発生したガス(水素、酸素など)はガスクロマトグラフで分析します。
 光触媒反応装置。こんなのが合計3台あります。
光触媒反応装置。こんなのが合計3台あります。
光触媒の構造はX線回折、電子顕微鏡、物性・電子構造は紫外可視反射スペクトル、蛍光スペクトル、X線光電子分光などで調べます(研究室と機器分析センターの機器)。また、半導体のバンド構造を理論計算して実験結果と比較検討します。
![]() Q どんな光触媒材料を研究しているの?
Q どんな光触媒材料を研究しているの?
うちのグループの得意分野の一つは層状物質。層と層との隙間に異なる物質を挟み込んだ、サンドウィッチ状の複合構造を容易につくることができます。半導体から構成される層状物質を使えば、挟み込む物質(サンドウィッチの具)によって電子状態も変化し、高い活性が発現すると期待してます。
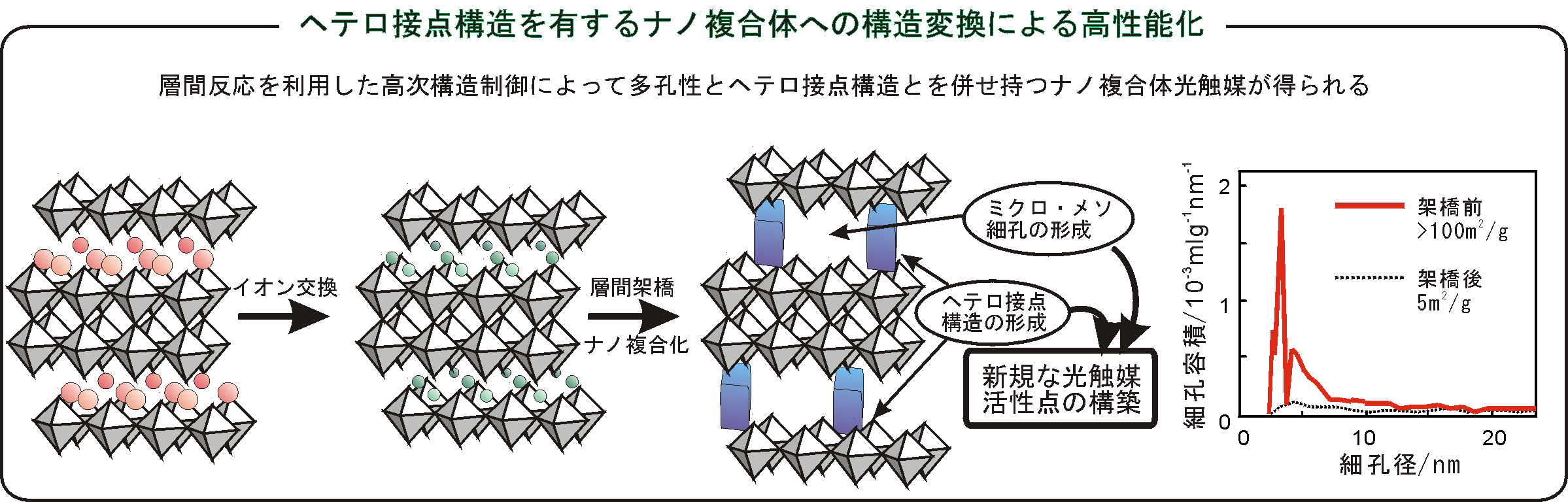
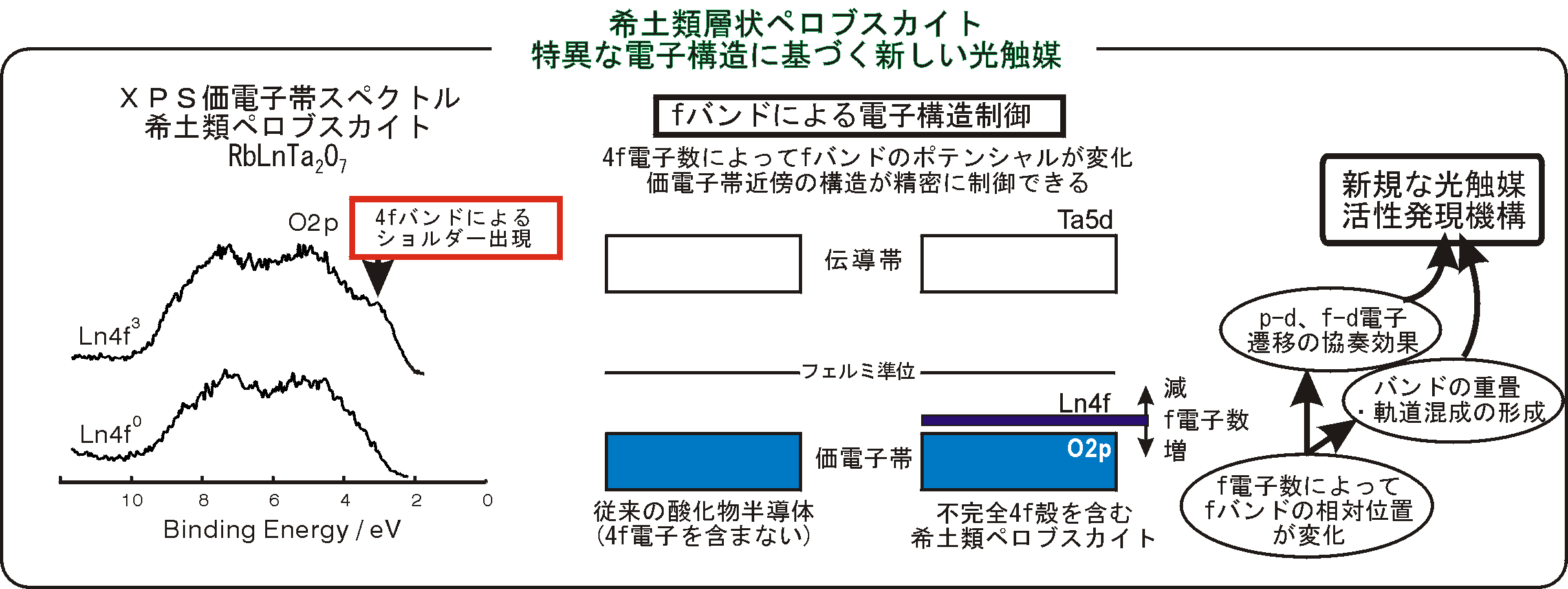
![]() Q まだまだあるエネルギー関連触媒
Q まだまだあるエネルギー関連触媒
ちょっと光触媒に力入れすぎて疲れてきましたのでそろそろやめますが、うちのエネルギー関連触媒は光触媒だけではありません。次に示す触媒についても研究を進めてます。詳しくはリンク先を参照してください。